更新:2025/03/17
小渋川変電所敷地造成に対する環境保全の見地からの意見募集
超電導リニアは、ガイドウェイのある一定の区間(約25㎞)の全体が一つのモーターです。回転する普通のモーターでいえば、列車が回転する部分、ガイドウエイが周りのコイルの部分にあたります。ガイドウェイの側に列車の位置に合わせて、列車の速度に応じた周波数と電圧の電力を流すための施設(インバータ*)が必要で、JR東海は実験線では「電力変換所」と呼んでいますが、一般向けには「変電所」といっています。その変電所を、小渋川非常口のそば、現在はトンネルの掘削残土の仮置場に使っている土地に建設する計画です。
この「小渋川変電所」の場所は、1961年の梅雨前線豪雨災害の時には浸水したし、対岸には鳶ヶ巣崩壊地(アカナギ)という標高差500m以上にもなる大崩壊地があり、災害時にはかなり危険な場所です。変電所の敷地として土地をかさ上げするのは災害への対策なのかも知れません。敷地は小渋川に面した部分の擁壁内に要対策土を使います。内側(敷地側)が鉄板(鋼板)で、外側(河川の側)がコンクリートでその間に要対策土を詰め込みます。小渋川で土石流が起きたとき本当に大丈夫なのか。下流には集落や農地があります(航空写真)。
南アルプストンネル長野工区からは、現在のところ、約17000㎥の要対策土(有害残土)が出てきました。5000㎥は変電所予定地に、残り1万2000㎥はトンネル坑内に保管してあります。
「要対策土の活用」、実は「処分の先送り」の無責任
保全計画は2017年1月に出された保全計画に追加修正したものです(主な追加部分)。保全計画によれば、敷地の周囲の擁壁部分に約1万㎥の要対策土を鉄板やコンクリートで閉じ込めるかたちで「活用」する計画。もともと、要対策土を敷地内の盛り土部分にも使うつもりだったのですが、要対策土から有害物が水に溶け出さないようにする不溶化処理の効果が、建物の基礎工事や杭打ちが原因でその効果がなくなる、低下する可能性があるので、普通の残土約4万㎥を使うことにしたと書いています。
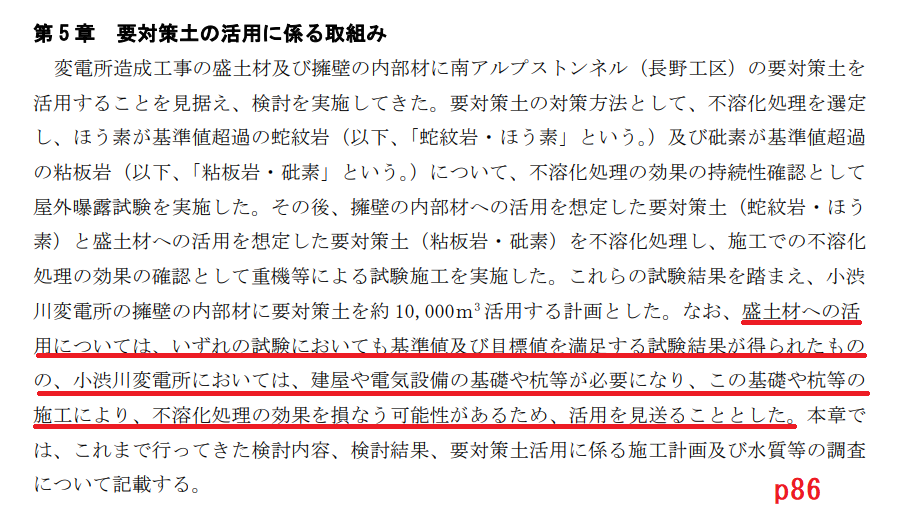
「中央新幹線南アルプストンネル新設(長野工区)工事における環境保全について [・南アルプストンネル(長野) ・小渋川変電所敷地造成] 2025年2月26日更新」のp86より
使わないならいいじゃんということにはならないですよね。
変電所はJR東海が購入した土地ですから自社用地です。JR東海は、要対策土は、自社用地で活用したい、ほかに公共事業で活用してもらいたいといって来ました。
公共事業で使う場合、その土地の上で将来、なにか開発行為がある場合、基礎工事をしたり杭を打つ可能性がある開発は簡単にはできないことを自ら示しているわけです。
将来、なにか開発をしようとすると、工事をするには、地下にある要対策土は、制度上は汚染土壌となるので、土を取り出して、きちんとした処分場に運んで処分する必要が出てくるはずです。それが「将来」じゃなくて、3分待たなくても、要対策土が、そのまま法律で規制される汚染土壌に化けるのに気が付いたので、JR東海さんは、保全計画にこういうことを書いたんじゃないかと思います。
自社用地では、もうこんな間抜けなことはしないと思います。公共事業での活用は「活用」じゃなくて「処分」の先送りです。こんなことを書くなんて、JR東海さんの自爆行為?
ところで、長野県は「環境保全の見地からの御意見をお持ちの方」はこの保全計画書について意見を寄せてくださいといっています。
今回の保全計画の追加部分は、小渋川変電所の敷地造成と小渋川橋りょう工事を行うための工事用トンネルの掘削についてです(主な追加部分)。
- 長野県:「中央新幹線南アルプストンネル新設(長野工区)工事(南アルプストンネル(長野)・小渋川変電所敷地造成)」に対する環境保全の見地からの御意見をお寄せください
- JR東海の保全計画:中央新幹線南アルプストンネル新設(長野工区)工事における環境保全について
長野県知事は、「報告書に対して、事業の実施に伴う環境への影響が最大限回避・低減されるよう、環境影響評価技術委員会・地元自治体からの意見聴取及び住民等の意見募集を実施した上で、環境保全の見地から助言を行う」ことになっています。
締め切りは、4月9日必着となっています。
「要対策土の活用」、実は「処分の先送り」の無責任なんですが、別のみかたをすれば、狭い国土で使える土地が減るということでもあるので、リニアはJR東海さんの「本来の鉄道用地」以外に、使えない土地を増やすことになるので、トンネル工事を主体とするリニア新幹線計画はそもそも我が国では許されない計画だったと思います。
長野県環境評価技術委員会の会議録を読むと、要対策土の発生量について、JR東海は予測できないと説明しているので(*)、この計画の無謀さはJR東海自身も十分知っているはずで、でありながら、要対策土処理(活用)について住民説明会で、皆さんが食べるヒジキ(**)にもヒ素が入っているんですよみたいな、安全性を強調する説明を繰り返してきたことは悪質というしかないです。
* 長野県内の残土の発生量に対して、これまで要対策土は約2万3千㎥で約1パーセントですが、JR東海は、これからどれほどの量が出てくるのかという問いに対して次のように説明しています。
要対策土の発生率、あるいは発生する可能性におきましては、もともと山の由来ですとか、掘っていく地質・地層、そういった観点でも非常に重要でございます。
そういった意味では、まだこれから南アルプストンネル長野工区につきましては、どんどんいわゆる土被りが高いところに向かって今掘削を進めているところでございますが、おそらくこれから先は、要対策土の出やすいかもしれない区間に入っていくという当社の見立てですので、現段階で割合が低いからといって、これから先も同様の割合で出てくるかと言われると、そこは楽観視できないと我々は考えているところでございます。
先ほど土被りが高いと申し上げましたが、土被りが高いということは、すなわち事前の調査がなかなかしにくいというところでございまして、土被りが1,000m、1,300mあるところですと、事前に鉛直ボーリングを打って要対策土の様子等を事前にチェックすることがなかなか難しいものですから、そういった意味でも、トンネルを掘りながら日々日々要対策土の発生の有無を確認して、その都度対応を取るというのが、今進め方として我々が取り組んでいるところでございます。…
したがいまして、最終的に何万m3出るというところの見込みが、今確定的に申し上げられませんので、それに伴って計画が立てにくいというのは正直なところではあるんですけれども、まずはこういった自社用地の活用を最大限進めると。その上で、今長野県をはじめ各自治体の方々に御協力の御依頼をしているところではございますが、例えばほかの事業ですとか、あるいは我々のほうで用地を取得させていただいて、発生土置場としてこういうものは活用できないかといった可能性を、まだ多角的に探っている状態でございます。(長野県環境影響評価技術委員会・2024年9月27日会議録(R6年度第6回))
つまり、環境保全の観点で非常に需要な問題なのに、着工から約10年になる現在でも全然見通しがたたない。何とかなるさではじめて、結局どうにもならなくなってしまったというのが現状でしょう。こんなことが許されてよいわけはなく、これは2014年のアセスに対する環境大臣の意見も指摘していたことで、国交大臣の建設工事の認可は明らかに間違っていたと思います。
** 元素について解説している本(たとえば、ブルーバックス『元素118の新知識』のような)を見ると、ヒジキに含まれるヒ素は有機ヒ素。摂取しても中毒の可能性はないと説明されています。海産物に含まれる有機ヒ素はそのまま尿中に排出され、ほとんどないけれど無機ヒ素の場合は肝臓でメチル化され尿中に排出される排出されるとされます(p196)。しかし、ヒ素を含む残土を要対策土として区分しているのはそれなりの意味があるはずです。また、なぜか? JR東海は住民向けにはヒジキの話を使うのですが、専門家である技術委員会に対する説明ではヒジキの話はしていません。
注* 新幹線だけでなくJRの在来線や私鉄でも新しい電車はインバータを積んでいてモーターを制御しています。たいていは車体の床下に積んでいます。こういう電車のインバータからモータまでの距離はたいしたことはないですが(16両編成新幹線の長さは約400m)、リニアの場合は、インバータからガイドウェイに配置されたコイルまでの配線する電線の長さは変電所(インバータ)が担当する距離(約25㎞)が基本になります。すごく無駄です。
注:新たに追加された部分は主なものは:
- p1、p2、p3
- p7、p8
- p15(工事用トンネル断面図あり)~p21
- p30
- p47~p49
- p57
- p59
- p68
- p82
- p86~p96
EoF